


午前8:30~11:30
午後13:30~16:30


2024/10/21

食物経口負荷試験(OFC; oral food challenge)とは、アレルギーと分かっている、または疑いのある食材や食品を医療機関で実際に食べ、その後の反応を観察していく検査です。
アレルギーのある食物を口にする場合、皮膚や呼吸、おなかなどに症状が現れるリスクが少なからずあります。
家で食べて、万が一アレルギーの症状が出てしまった場合、準備がないと治療・対応が遅れ、症状がさらに悪化してしまう可能性もあります。
食物経口負荷試験は、食べる前後の様子や食べた後の状態を診察・チェックし、症状出現時には医師・看護師がすぐ対応できるよう医療機関で環境を整えて実施します。
食物アレルギーの診断は血液検査だけでは確定できず、食物経口負荷試験で実際に口にして、症状が出るかを確認することが一番確実な診断方法です。
詳しく問診を行い、明らかな因果関係が分からない場合は、アレルギーが疑われる食品の試験を計画します。
また、今まで食べたことがないものの、検査などからアレルギーの可能性がある食品を食物経口負荷試験で初めて食べる例もあります。
特定の食品にアレルギーがあっても、少量または特定の調理法・加工法なら食べられることも少なくありません。
また、症状を起こさない最低限の量を定期的に食べることで、耐性ができる確率が上昇します。
その量の評価・耐性獲得の確認のために、食物経口負荷試験を行います。
なお、食物アレルギーの中でも小さいお子さんの症例、特に3大アレルゲンと呼ばれる卵・牛乳・小麦については、成長することで耐性がつき、食べても症状が起こらなくなるという症例が多いです。

安全に試験を行う・リスクを極力避ける目的も含めて、まずは患者さんの診察・過去の症状が現れた時の症状や経過の確認、既往歴・家族歴の聴き取りなどを行います。その結果、食物アレルギー以外の病気が原因と判明することもあります。
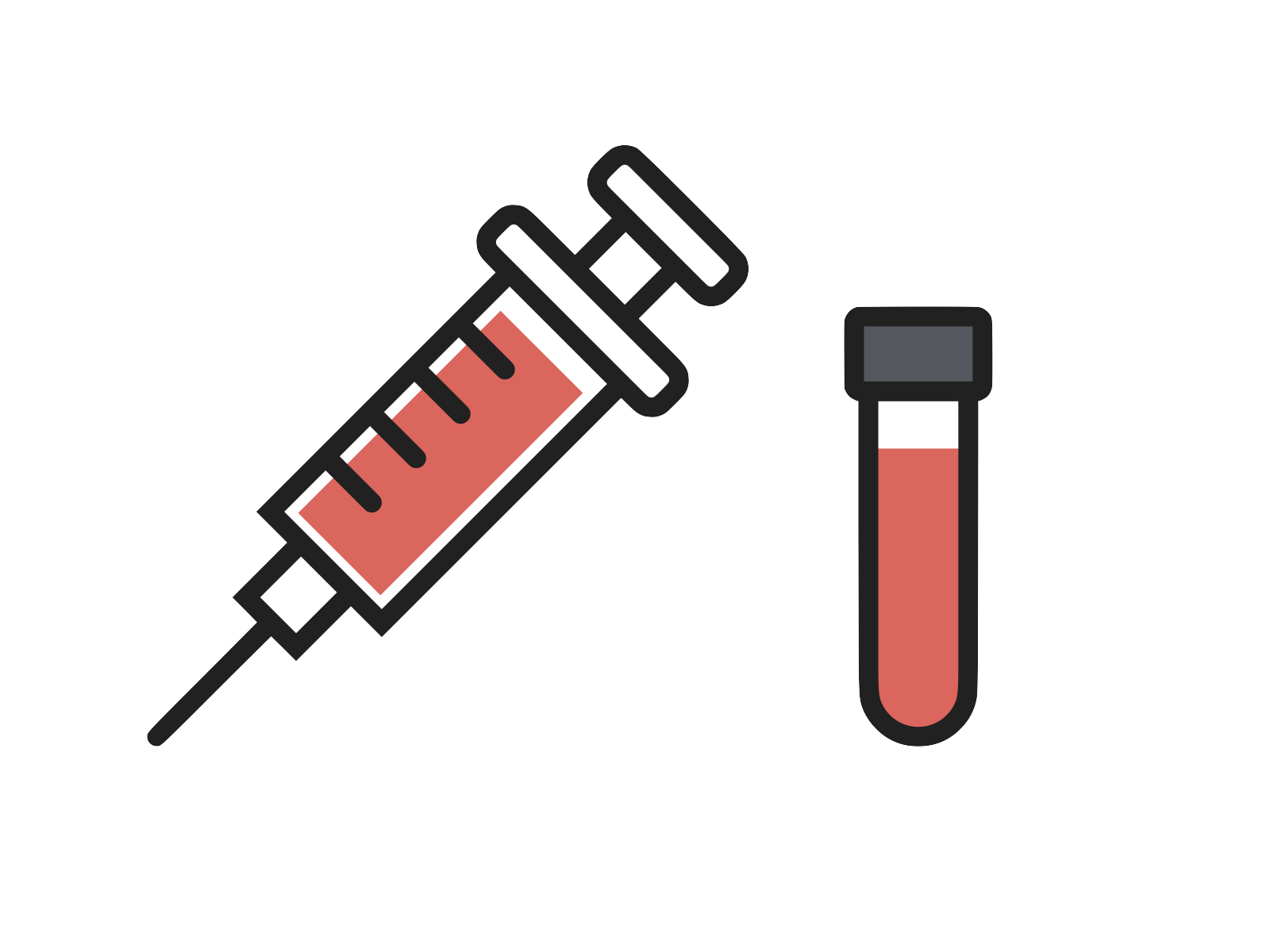
診断および食物経口負荷試験前のサポートとして、血液検査などの他の検査を行う場合もあります。
たとえば、血液検査によって行う特異的IgE抗体検査は、アレルギーの疑いのある食品・成分を評価するための補助的な指標となります。アレルギー症状がどれくらいの確率で起こるか評価し、食べる量を決定する上での目安に用います。

食物アレルギーの患者さんは、アトピー性皮膚炎や気管支喘息などの他のアレルギー疾患を合併する方も多く、他にも呼吸器や心臓などの基礎疾患がある方もいます。
食物経口負荷試験では、強い症状が発症しやすい要因の一つとして、他の病気の影響(たとえば風邪などで全身状態が悪い場合、基礎疾患やアレルギー疾患のコントロールが悪い状態)が挙げられます。
このような場合は、検査の前に合併症の治療・管理を行うことが望ましいです。それらを経て、問題ないと評価したうえで検査の予定を立てていきましょう。

何を・どのくらいの量食べるか、1回で食べるか・2回に分けて食べるか、食べてもらった後にどれくらい観察するかなど、個人に合わせて決めて、万が一の症状出現時に備えて、治療の内服薬をあらかじめ処方します。
なお、アレルギーの内服薬をはじめ、定期的にお薬を内服されている場合、食物経口負荷試験の経過に影響を及ぼす可能性があるため、検査前数日から内服を一時中止していただく必要があります。
当院では、負荷後の観察や症状出現時の対応を速やかに行えるよう、日帰り入院で病棟での実施を基本としています。
発疹や咳・呼吸苦、嘔吐などのアレルギーと考えられる症状が出た場合、"陽性"と評価されます。
すぐに検査を中止して診察し、症状の強さによっては内服薬・点滴/注射薬・吸入などの治療を開始します。
症状が軽度の場合は、治療を行わずに観察することもあります。
アナフィラキシーなど強いアレルギー症状が出た場合は、アドレナリンの筋肉注射も行います。
症状が長く出現している、または一度改善しても再び悪化するリスクが心配される場合、退院を延期して翌日まで観察を続けます。
陰性だった場合、検査で食べた量は自宅でも摂取可能となります。
1日おき、または週2~3回ほど練習として食べ、外来診察で症状を確認します。症状がなければ、練習での摂取量を徐々に増やしていきます。
なお、保留や陽性であっても、今後一切食べられないというわけではなく、これまでに摂取可能だった形態・量は継続して食べることを指導させていただきます。または、期間をおいて、再度同食品の試験を実施することを計画します。
他の食物アレルギーもある場合、その食物の検査を実施することも提案いたします。
お子さまの食物アレルギー検査(食物経口負荷試験)をご希望の方は、まずは小児科の外来診察が必要になりますので、下記よりご予約ください。
※紹介状がなくてもご受診いただけます(特別料金は不要)
【予約センター】
086-422-2112
(受付 平日9:00~16:00)
